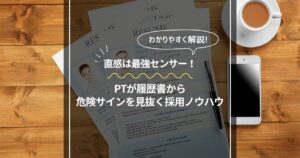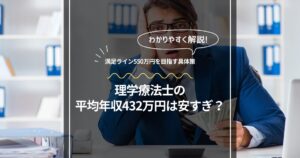JFAメディカルセンター不正請求問題から考える、理学療法士に必要なガバナンスと外来整形外科の診察要件の難しさ
2025年4月、公益財団法人日本サッカー協会(JFA)が福島県楢葉町で運営する「JFAメディカルセンター」において、実際には行っていない医師の診察を行ったと虚偽申告し、2021年5月~2023年8月にかけて数千万円規模の診療報酬を不正請求していたことが明らかになりました。本件は東北厚生局から戒告処分を受け、調査完了後に全額返還が約束されています。理学療法士として患者さんの信頼を守るうえで、法令遵守とガバナンス体制の重要性は今後ますます高まるでしょう。さらに、外来整形外科では毎回医師の診察を経なければ保険請求できないという要件があり、その運用の難しさも合わせて考えていきます。
不正請求の手口と背景
- 虚偽の診察申告
診療報酬制度では「医師の診察」が前提ですが、実際には医師が診察していないにもかかわらず初診料や再診料を請求。 - 記録要件の不履行
リハビリ開始・終了時間や処置内容のカルテ記載を怠り、必要書類を整えないまま報酬請求。 - 施設再開直後の混乱
東日本大震災後に2021年3月に再開し、患者数増加に伴う待ち時間短縮を理由としたとの報道。
「患者を待たせたくない」という意図は理解できても、法令遵守をないがしろにすれば患者だけでなく組織全体の信頼を失います。
外来整形外科における診察要件の難しさ
- 毎回の医師診察
外来整形外科では、保険診療で理学療法を行う際に「医師の診察・指示」が介在しなければなりません。たとえば、- 患者受診
- 医師がリハビリ指示書を発行
- 理学療法実施
という流れが原則ですが、忙しい医師と物理的に空き枠の少ないスケジュール調整は容易ではありません。
- 時間的・人的コスト
患者さんを診察室に案内し、医師が対面で確認・記録する手間と時間は、クリニック全体の診療効率に直結します。 - 緊急性と継続性のバランス
ケガや痛みの再発予防には継続的リハビリが不可欠ですが、診察枠が埋まっていると必要なタイミングでのリハビリが行えず、患者満足度や治療効果にも影響します。
理学療法士に求められる法令遵守とリスク管理
- カルテ記載の徹底
開始・終了時間、実施内容、患者の変化と次回予定まで詳細に記録し、第三者が見ても不正がないことを裏付ける。 - 診療報酬制度の定期アップデート
厚労省や地方厚生局からの通知・告示をこまめに確認し、改定事項をスタッフ全員で共有。 - 疑義照会の活用
処置や請求項目に不安があれば、速やかにレセプトコンピューターや審査支払機関へ疑義照会を行い、クリニック全体で対応を統一。 - 内部通報・相談体制の整備
小さな違和感にも報告しやすい仕組みを構築。「自分だけが知らなかった」リスクを防ぐために、匿名でも相談可能な窓口を設置。
組織のガバナンス強化策
| 項目 | 具体例 |
|---|---|
| 定期監査 | 月次のサンプル抽出によるカルテ・請求データのチェック |
| 研修プログラム | 法改正・制度運用のeラーニング導入、全員受講義務 |
| IT活用 | タイムスタンプ付き記録管理システムで記録改ざんを防止 |
| リスク共有会議 | 月1回のリスクマネジメント会議で問題発生状況と対策を報告 |
| 評価制度 | コンプライアンス遵守度を人事評価に反映、定期的フィードバック |
患者との信頼関係を最優先に
- 透明性の確保:リハビリ内容や頻度、診察の必要性を患者に説明し、なぜ毎回医師の診察が必要かを理解してもらう。
- 効率的な予約管理:医師と理学療法士のスケジュールを一体管理し、診察とリハビリがスムーズに連携できる枠組みを構築。
- 継続的コミュニケーション:疑問や不安を患者から引き出し、迅速に対応。信頼が生まれれば、診察・リハビリ両面で無理のない運営が実現します。
おわりに
JFAメディカルセンターの不正請求問題は、医療従事者としてのコンプライアンス意識の欠如と組織的ガバナンスの脆弱性を浮き彫りにしました。理学療法士としては、外来整形外科特有の「毎回診察要件」というハードルを正しく運用しつつ、法令遵守とリスク管理を徹底することが求められます。患者さんの安全と信頼を守るため、自施設の運営体制を今一度見直し、改善を図りましょう。
関連サイト
https://www.japan-sports.or.jp
公益財団法人日本パラスポーツ協会(JPSA)
日本パラスポーツ協会(JPSA)は、国内における三障がいすべてのスポーツ振興を統括する組織で、障がい者スポーツ大会の開催や奨励、障がい者スポーツ指導者の育成、障がい者のスポーツに関する相談や指導、普及啓発などを行っています。