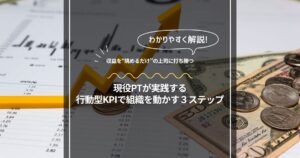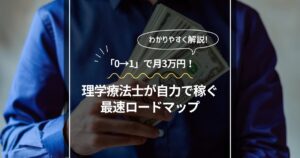【現場の停滞を打破せよ】業務改善に動かない管理者の下で、理学療法士ができること
「どう考えてもこのやり方は非効率……なのに誰も変えようとしない」
そんなジレンマを抱えたことはありませんか?
医療・介護の現場では、日々の業務改善が不可欠です。しかし、現場トップの管理者が改善に関心を持たず“現状維持”を選び続けるケースは少なくありません。本記事では、理学療法士として働くあなたが、そんな環境でどう考え、どう動くべきかを掘り下げます。
業務改善に取り組まない管理者の特徴
1. 変化を恐れる「前例主義者」
「前からこうしているから」「これで問題は起きていない」という言葉で新しい挑戦にブレーキをかけがちです。
2. 評価制度が安定志向
医療機関では、管理者が「混乱を起こさないこと」で評価される場合があります。新しい取り組みはリスクと見なされ、避けられがちです。
3. 臨床から離れ現場感覚が薄れる
管理者が現場から遠ざかると非効率に気づかず、改善意欲を削がれます。
“改善放置”が招く具体的な弊害
| 状況 | 放置された業務 | 引き起こすリスク |
|---|---|---|
| 手書き→電子カルテ未導入 | 二重記録・入力ミス | 残業増、離職 |
| 情報共有が口頭・紙頼み | 情報抜け漏れ | 医療事故 |
| 記録様式がバラバラ | 記録内容の差異 | ケア品質低下 |
| 発注が属人的 | 在庫過剰・不足 | コスト増 |
| 課題が未共有 | 問題が長期化 | 組織風土悪化 |
理学療法士ができる5つの改善アクション
- 小さな成果を数値で“見える化”
例:SOAP記録テンプレ統一で週5分短縮など、具体的な数字が説得力を高めます。 - 提案は“A4一枚”にまとめる
他院事例やコスト比較を簡潔な資料にすると、思いつきではないと示せます。 - 横のつながりで改善チームを作る
若手・中堅で横断的に組み、管理者を“スポンサー”役に据えると協力を得やすいです。 - 院外で成果を発信する
学会発表や院内報告会に乗せれば、組織として無視できない空気をつくれます。 - “やらない損失”を数字で示す
例:記録ミス1件=○○円のロスなど、放置コストを明示すると関心を引けます。
管理者を動かすコミュニケーション術
- 感情ではなく事実で語る
データや具体例で改善の必要性を提示。 - 問いかけで気づきを促す
「このまま来年度を迎えると算定要件への影響は?」と切り出します。 - 共通ゴールを示す
「患者アウトカム向上」「残業削減」など共有指標を掲げましょう。 - 意思決定のタイミングを狙う
月次報告会や診療報酬改定前などに提案すると通りやすいです。
それでも動かない管理者の下での選択肢
- 自部署だけでも改善を継続
小さな成功例を社内共有し、波及効果を狙います。 - 副業・学会活動で院外ネットワークを持つ
外部での評価が院内での発言力を高めます。 - 改善文化のある職場へ転職も視野に入れる
成長機会を奪われ続けるより、環境を変える方がキャリアにプラスです。
まとめ:変化を起こすのは“現場の一歩”から
業務改善とは、小さな不満を「じゃあどうする?」に変える力です。それを動かすのは「誰か」ではなく「あなた」の行動。まずは一つ、今日できる改善を始めてみませんか? 現場からの一歩が、組織も医療も、そして患者さんの未来も変えていきます。
関連サイト
JSPO 日本スポーツ協会
わが国におけるスポーツ統括団体「JSPO(日本スポーツ協会)」の公式サイト。国民体育大会や日本スポーツマスターズの開催、スポーツ少年団の運営など。
公益財団法人日本パラスポーツ協会(JPSA)
日本パラスポーツ協会(JPSA)は、国内における三障がいすべてのスポーツ振興を統括する組織で、障がい者スポーツ大会の開催や奨励、障がい者スポーツ指導者の育成、障がい者のスポーツに関する相談や指導、普及啓発などを行っています。