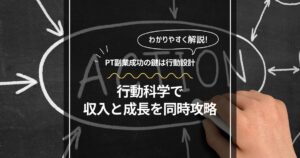- 1. 足を引っぱり続ける人の心理と対処法——理学療法士が知っておくべき組織行動のリアル
- 1.1. はじめに
- 1.2. 第1章:足を引っぱる人の特徴とは?
- 1.3. 第2章:心理学的に読み解く“足を引っぱる人”の背景
- 1.3.1. 1. 社会的比較理論(Festinger, 1954)
- 1.3.2. 2. 自己ハンディキャッピング(Jones & Berglas, 1978)
- 1.3.3. 3. ダークトライアド傾向
- 1.3.4. 4. 組織的公正感の欠如(Adams, 1965)
- 1.3.5. 5. 学習性無力感(Seligman, 1975)
- 1.4. 第3章:理学療法士の職場で起こりがちな足の引っぱり行動
- 1.4.1. 1. 情報を共有しない
- 1.4.2. 2. 後輩を育てない
- 1.4.3. 3. 自分の成功にしか興味がない
- 1.4.4. 4. 陰で悪口や噂話を広げる
- 1.5. 第4章:現場でできる対処法
- 1.5.1. 1. フィードフォワード面談を取り入れる
- 1.5.2. 2. ピアレビューを導入する
- 1.5.3. 3. 公平な評価制度の設計
- 1.5.4. 4. 心理的安全性の醸成
- 1.5.5. 5. ジョブ・クラフティングの活用
- 1.6. 第5章:足を引っぱる人を放置するリスク
- 2. まとめ
足を引っぱり続ける人の心理と対処法——理学療法士が知っておくべき組織行動のリアル
はじめに
どの職場にも存在する“足を引っぱり続ける人”。他人の成功を妬んだり、情報を共有しなかったり、陰で悪口を言ったり……。
理学療法士という専門職であっても例外ではありません。多職種連携が前提となる医療現場において、こうした行動は患者ケアに直接的な悪影響を及ぼすことすらあります。
本記事では、心理学的な知見と組織論をもとに、「なぜ人は他人の足を引っぱるのか?」「そうした人が生まれる土壌とは?」「対処法はあるのか?」を深掘りします。理学療法士としてチームで働くあなたにとって、実践的で腑に落ちる内容をお届けします。
第1章:足を引っぱる人の特徴とは?
職場で“足を引っぱる人”とは、必ずしも直接的な妨害行為をする人だけではありません。以下のような特徴に心当たりはありませんか?
- 情報を独占し、共有を渋る
- 成果よりも他人のミスを探す
- 会議では否定的な意見ばかり述べる
- 指示待ち傾向が強く、自発的に動かない
- 新しい取り組みに対して「やってもムダ」と冷笑する
- 他人の成功や挑戦を皮肉る
こうした言動は、組織の生産性やモチベーションを低下させるだけでなく、医療サービスの質を損ねることにもつながります。
第2章:心理学的に読み解く“足を引っぱる人”の背景
1. 社会的比較理論(Festinger, 1954)
人は自分と似た立場の他者と比較することで自己評価を行います。他人の成功が脅威に感じられると、無意識のうちにその人の失敗を期待するようになったり、邪魔をしてしまうこともあります。
2. 自己ハンディキャッピング(Jones & Berglas, 1978)
「失敗したときの言い訳」を事前に用意しておく心理です。職場での例としては、仕事の締切をわざと遅らせたり、情報を握りつぶしておいて「教えてもらっていないから」と言い訳するような行動が当てはまります。
3. ダークトライアド傾向
心理学で知られる「ナルシシズム(自己愛)」「マキャベリズム(操作性)」「サイコパシー(共感性の欠如)」という三要素。これらの傾向が高い人は、チーム内で信頼関係を築くよりも自分の立場を守ることに意識が向きます。
4. 組織的公正感の欠如(Adams, 1965)
努力に見合った評価が得られないと感じると、人は「頑張っても意味がない」と考えます。その結果、他人の努力を否定したり、組織の足を引っぱる行動に転じることがあります。
5. 学習性無力感(Seligman, 1975)
何度やっても成果が出ない、評価されない経験が積み重なると、やがて「どうせ何をやってもムダ」という諦めが支配します。この無気力が他人への無関心や冷笑的な態度につながります。
第3章:理学療法士の職場で起こりがちな足の引っぱり行動
理学療法士の職場では、特有の構造や評価制度が“足を引っぱる人”を生み出しやすくしています。
1. 情報を共有しない
カンファレンスでの発言が少なく、患者の反応や注意点を報告しない人がいます。これは結果としてリハビリの質を下げる要因になります。
2. 後輩を育てない
新人や後輩に対して指導をせず、「見て覚えろ」という態度をとる。あるいは、意図的に重要な情報を伏せるなど、教育的配慮が欠如しているケース。
3. 自分の成功にしか興味がない
チームの成果よりも、個人の評価を最優先し、他者との協働を避ける傾向があります。報告書や実績データを独占しがちです。
4. 陰で悪口や噂話を広げる
直接は何も言わないのに、裏で他人の評判を落とすような発言をすることで、職場の空気を悪化させます。
第4章:現場でできる対処法
1. フィードフォワード面談を取り入れる
過去の失敗を責めるのではなく、「次にどう動くか」に焦点をあてた対話を行う。これにより、攻撃的な姿勢ではなく、建設的な意見交換が促されます。
2. ピアレビューを導入する
医師や他職種と同様、理学療法士間で相互にフィードバックをし合う文化をつくる。特に情報共有率や協働姿勢など“見えにくい行動”を評価対象に含めるのがポイントです。
3. 公平な評価制度の設計
単なる数値成果ではなく、チームへの貢献度や教育活動も評価に加えることで、自己中心的な行動のインセンティブを減らすことができます。
4. 心理的安全性の醸成
「質問する」「提案する」「助けを求める」といった行動が否定されない雰囲気づくりが必要です。上司やリーダーが率先して、オープンな対話を日常に取り入れましょう。
5. ジョブ・クラフティングの活用
足を引っぱる人の中には、自分の仕事にやりがいや適性を感じていないケースもあります。本人の強みや興味に合わせてタスクを再設計することで、前向きな行動へと転換できる可能性があります。
第5章:足を引っぱる人を放置するリスク
“あの人はそういう性格だから”と見て見ぬふりをすることには、以下のような重大なリスクがあります。
- 若手職員の離職が加速
- カンファレンスやチームカンファの機能不全
- 医療事故の温床
- チーム内の信頼関係の崩壊
- 管理職の統制力低下
悪影響はじわじわと、しかし確実に組織全体に波及します。だからこそ、見過ごすのではなく、段階的な対応と組織全体の風土改革が求められます。
まとめ
足を引っぱり続ける人の背景には、心理的な要因・環境要因・制度的な要因が複雑に絡み合っています。彼らの行動を単に“性格の悪さ”で片付けるのではなく、行動の意味や背景を理解し、適切な対応をとることが、職場全体の健全性を保つ鍵となります。
理学療法士として、自分自身がそうならないよう気をつけるのはもちろん、周囲の足を引っぱる行動にどう向き合うかもまた、専門職としての重要なスキルのひとつです。
「変わらない人」を責めるのではなく、「変われる環境」をつくる。その一歩を、あなたの職場からはじめてみませんか?
関連サイト
JSPO 日本スポーツ協会
わが国におけるスポーツ統括団体「JSPO(日本スポーツ協会)」の公式サイト。国民体育大会や日本スポーツマスターズの開催、スポーツ少年団の運営など。
公益財団法人日本パラスポーツ協会(JPSA)
日本パラスポーツ協会(JPSA)は、国内における三障がいすべてのスポーツ振興を統括する組織で、障がい者スポーツ大会の開催や奨励、障がい者スポーツ指導者の育成、障がい者のスポーツに関する相談や指導、普及啓発などを行っています。