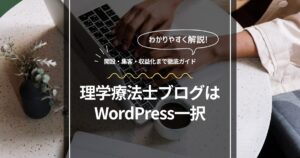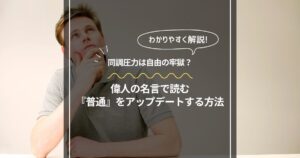- 1. 理学療法士が“無料ブログ”を選ぶべきではない決定的な理由
- 1.1. はじめに
- 1.2. 1. 理学療法士が今こそブログを始めるべき3つの背景
- 1.2.1. 1-1. 患者の情報収集行動の変化
- 1.2.2. 1-2. キャリアパスの多様化
- 1.2.3. 1-3. 学術的アウトプットの最適化
- 1.3. 2. 無料ブログサービスの基本仕様と“甘い誘い”
- 1.4. 3. 無料ブログを勧めない10の理由
- 1.4.1. 3-1. ドメインの信用力とE-E-A-Tの欠如
- 1.4.2. 3-2. 運営会社広告による収益機会の損失
- 1.4.3. 3-3. SEOカスタマイズ制限で検索上位に届かない
- 1.4.4. 3-4. サービス終了リスクとデータ消失の恐怖
- 1.4.5. 3-5. 拡張機能不足で将来のビジネス展開が困難
- 1.4.6. 3-6. データ所有権の曖昧さと機密情報流出リスク
- 1.4.7. 3-7. 表示速度の遅延が離脱率を高める
- 1.4.8. 3-8. サポート体制が脆弱でトラブルに弱い
- 1.4.9. 3-9. デザイン統一ができずブランド力が下がる
- 1.4.10. 3-10. 引っ越しコストが雪だるま式に膨らむ
- 1.5. 4. 失敗事例に学ぶ:無料→有料へ移行せざるを得なかったPTのケーススタディ
- 1.6. 5. 月1,000円の投資が“臨床経験”を資産に変える――有料ブログ4大メリット
- 1.7. 6. 【実践ガイド】最短1日でWordPressを立ち上げる手順
- 2. まとめ:専門職こそ“最初から”有料で始めるべき
理学療法士が“無料ブログ”を選ぶべきではない決定的な理由
はじめに
「まずはお金をかけずに始めたい」――そう考えて無料ブログサービスに手を伸ばそうとしていませんか?
しかし、リハビリの専門家として情報発信を始める理学療法士にとって、無料プランは“お得”どころか致命的なリスクをはらんでいます。本記事では、理学療法士がブログ運営でつまずきやすいポイントを踏まえながら、無料ブログを勧めない理由と、有料で立ち上げるメリットを徹底解説します。
1. 理学療法士が今こそブログを始めるべき3つの背景
1-1. 患者の情報収集行動の変化
コロナ禍以降、通院前にリハビリ情報をネット検索する患者が急増しています。検索結果にあなたの記事があれば、自然と“地域の専門家”として認知が広がります。オンラインでの信頼形成は、初診時の緊張を和らげ、治療へのエンゲージメントを高める効果も期待できます。
1-2. キャリアパスの多様化
病院・施設勤務だけでは年収が頭打ちになる現実は避けられません。オンライン講座、自費リハビリ、書籍出版など、発信を起点にした複数の収入チャネルが注目されています。ブログはそのハブとして機能し、あなたの臨床経験が文字どおり“稼ぐ資産”に変わります。
1-3. 学術的アウトプットの最適化
学会発表や抄録で埋もれがちな症例報告をブログ記事として公開すると、同業からの引用や紹介が増えます。検索エンジンは経験・専門性・権威性・信頼性(E-E-A-T)を評価するため、専門情報を体系的に公開することで、あなた自身のブランド価値も高まります。
2. 無料ブログサービスの基本仕様と“甘い誘い”
代表的な無料サービス(Amebaブログ、はてなブログ、Note無料プランなど)は、
- 会員登録だけで即日投稿
- サーバー費0円、独自ドメイン不要
- テンプレート選択だけでデザイン完成
という“手軽さ”を武器にユーザーを集めています。しかしこの手軽さは、長期的な資産形成という視点で見れば大きな落とし穴となります。
3. 無料ブログを勧めない10の理由
3-1. ドメインの信用力とE-E-A-Tの欠如
医療・健康情報の発信では“信頼できるソースかどうか”が最重要です。〇〇.blog-service.comのようなサブドメインでは、検索エンジンも読者も専門性を正しく評価しにくいため、クリック率が下がります。
3-2. 運営会社広告による収益機会の損失
無料プランでは運営会社のバナー広告が自動挿入され、アフィリエイトや自費リハビリメニューを訴求しづらい構造です。広告収益を取りこぼすだけでなく、読者の離脱を招きます。
3-3. SEOカスタマイズ制限で検索上位に届かない
理学療法関連キーワードは競争が激しいにもかかわらず、meta description編集不可、Schema.org構造化マークアップ非対応、画像のWebP変換不可といった制限があり、上位表示の土俵にも立てません。
3-4. サービス終了リスクとデータ消失の恐怖
Yahoo!ブログ(2019年終了)のように、大手でも突然の閉鎖・規約変更が起こります。記事が消えることは、積み重ねた臨床ノウハウが一夜にして失われることを意味します。
3-5. 拡張機能不足で将来のビジネス展開が困難
予約システムやオンライン決済を組み込む際、無料プランでは外部連携が制限されがちです。自費リハビリの予約導線を作れないままアクセスだけを眺める状況に陥ります。
3-6. データ所有権の曖昧さと機密情報流出リスク
投稿コンテンツを運営会社が二次利用可能と明記しているケースもあります。症例写真や評価動画が無断転載される可能性はゼロではありません。
3-7. 表示速度の遅延が離脱率を高める
同一サーバーに多数の無料サイトが詰め込まれ、アクセス集中で表示が遅延します。Googleのコアウェブバイタル評価が下がり、検索順位も連動して下落します。
3-8. サポート体制が脆弱でトラブルに弱い
無料ユーザーは問い合わせ窓口がメールのみ、返信に数日かかることも珍しくありません。学会直前に参考記事が表示崩れを起こしても、自力で復旧するしかありません。
3-9. デザイン統一ができずブランド力が下がる
病院サイトやSNSとカラーを合わせたいのに、CSS編集がロックされていることがあります。ブランディングの一貫性が失われると、読者の記憶に残りません。
3-10. 引っ越しコストが雪だるま式に膨らむ
「とりあえず無料で」と始めた人ほど記事数が増えた頃に有料へ移行したくなります。パーマリンク変更、301リダイレクト、画像リンク修正……外注すると数十万円も覚悟が必要です。
4. 失敗事例に学ぶ:無料→有料へ移行せざるを得なかったPTのケーススタディ
症例解説記事が月3万PVを超えたAさんは、アメブロの広告だらけの表示に悩み、有料WordPressへの移行を決意しました。しかし
- 300本の内部リンク修正に50時間
- 設定ミスで旧URLが404となり検索流入50%減
- 画像リダイレクト作業で外注費12万円
と、時間とコストの両面で大きな痛手を負いました。Aさんは「最初から有料で始めればよかった」と語りますが、この後悔は決して他人事ではありません。
5. 月1,000円の投資が“臨床経験”を資産に変える――有料ブログ4大メリット
- 独自ドメイン=オンライン名刺
〇〇rehab.comというURLは専門家としての信頼を高め、学会ポスターや名刺に載せれば即ポートフォリオとして機能します。 - フルカスタマイズでSEO最適化
プラグインでパンくずリスト、構造化データ、AMP対応まで簡単。検索流入が安定し、患者・同業からの問い合わせが増えます。 - 多角的マネタイズが可能
アフィリエイト、セミナーLP、動画教材販売へシームレスに拡張でき、臨床スキルを収益化できます。 - データ完全所有
サーバー・ドメインの契約者はあなた自身。バックアップもSSL証明書も自由に管理でき、ライフワークとして運営できます。
6. 【実践ガイド】最短1日でWordPressを立ち上げる手順
| ステップ | 作業内容 | 目安時間 |
|---|---|---|
| ① サーバー契約 | ConoHa WINGなど国内高速サーバーを月1,000円前後で契約 | 10分 |
| ② 独自ドメイン取得 | .comまたは.jpを同時取得。医院名や専門分野を含めると◎ | 5分 |
| ③ WordPress自動インストール | 管理画面からワンクリック | 5分 |
| ④ 初期設定 | パーマリンク→「投稿名」、SSL化、プラグイン導入(SEO・高速化) | 30分 |
| ⑤ テーマ選定 | ブロックエディタ対応の有料テーマでデザイン統一 | 30分 |
| ⑥ 1st記事投稿 | 自己紹介+ブログの目的+専門領域を記載 | 60分 |
合計約2時間の作業で公開まで到達します。初期投資はサーバー+ドメインで年間15,000円前後。臨床経験を生かした記事1本で十分に回収可能です。
まとめ:専門職こそ“最初から”有料で始めるべき
理学療法士としてブログを運営する目的は、
- 専門知識を広め患者のQOL向上に貢献すること
- 臨床経験を資産に変え、キャリアと収入を拡張すること
この二大目的を達成するには、無料ブログの手軽さよりも“信頼・自由・拡張性”を優先すべきです。
たった月1,000円の自己投資が、未来のあなたと患者の可能性を広げます。無料という選択肢に惑わされず、今日から独自ドメイン×WordPressであなたの専門性を世界へ届けましょう。
関連サイト
JSPO 日本スポーツ協会
わが国におけるスポーツ統括団体「JSPO(日本スポーツ協会)」の公式サイト。国民体育大会や日本スポーツマスターズの開催、スポーツ少年団の運営など。
公益財団法人日本パラスポーツ協会(JPSA)
日本パラスポーツ協会(JPSA)は、国内における三障がいすべてのスポーツ振興を統括する組織で、障がい者スポーツ大会の開催や奨励、障がい者スポーツ指導者の育成、障がい者のスポーツに関する相談や指導、普及啓発などを行っています。