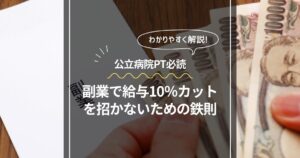- 1. はじめに
- 1.1. なぜ是正が難しいのか?5つの背景要因
- 1.1.1. 1. 心理的固定化と自我の強化
- 1.1.2. 2. 年功序列文化と同調圧力
- 1.1.3. 3. 法的・制度的制約
- 1.1.4. 4. 評価制度の曖昧さ
- 1.1.5. 5. 周囲の無関心・諦め
- 1.2. 現場で見られる問題行動の例
- 1.3. 是正への現実的アプローチ
- 1.3.1. ステップ1:記録と可視化
- 1.3.2. ステップ2:DESC法を用いた伝え方
- 1.3.3. ステップ3:第三者の介入
- 1.3.4. ステップ4:改善契約・段階的指導
- 1.4. 管理者・チームが取るべき中長期的な対策
- 1.4.1. 1. コンピテンシー評価の導入
- 1.4.2. 2. 組織文化のアップデート
- 1.4.3. 3. ピアレビュー・360度評価
- 2. まとめ
はじめに
医療や介護の現場では、経験豊富なスタッフが多数在籍する一方で、長年の勤務によって行動が固定化し、時には問題行動を起こす職員も見受けられます。現役の理学療法士として働いているあなたも、「あの人の対応にいつも困っている」と感じた経験があるのではないでしょうか。
特に年齢を重ねたスタッフに対しては、注意や改善を促すこと自体が大きなハードルとなります。本記事では、なぜ是正が難しいのかを深掘りし、現場で実践できる対策をプロの視点から徹底解説します。
なぜ是正が難しいのか?5つの背景要因
1. 心理的固定化と自我の強化
長年のキャリアによって「自分は正しい」「今さら誰に言われる筋合いもない」といった認知が強くなり、自己修正が困難になる傾向があります。これを心理学では「エイジング・リジディティ(加齢に伴う柔軟性の低下)」と呼びます。
2. 年功序列文化と同調圧力
医療現場には未だに根強く残る“年長者=偉い”という価値観。若手や中堅スタッフが問題行動を指摘しづらい空気が蔓延しています。言いづらさが沈黙を生み、結果として問題行動が放置されがちです。
3. 法的・制度的制約
労働基準法、高年齢者雇用安定法、パワハラ防止法などによって、高齢職員への対応には慎重さが求められます。明確な懲戒理由や証拠がなければ、法的リスクが高まり、管理者は動きづらくなります。
4. 評価制度の曖昧さ
勤続年数はあるが、行動評価や業務実績が定量的に測られていないケースが多々あります。結果、指導の根拠が弱くなり、曖昧な注意に終始してしまうことも。
5. 周囲の無関心・諦め
「何を言っても無駄」「もうすぐ定年だから我慢しよう」といった諦めムードが蔓延すると、チーム全体のモチベーションが低下します。沈黙は、結果的に問題行動を容認することにつながります。
現場で見られる問題行動の例
以下のようなケースは、理学療法士の現場でもよく見られます。
- 指示書や記録業務の遅延・誤記
- カンファレンスや会議中の居眠り、私語
- 若手へのマウント発言や冷笑的な態度
- 独自の手技や時代遅れの介入方法を正当化
- チームの意向に従わない単独行動
いずれも放置すれば、患者対応の質・チームワーク・業務効率に悪影響を及ぼす重大な問題です。
是正への現実的アプローチ
ステップ1:記録と可視化
感情ではなく事実で対処するために、問題行動の"記録"を始めましょう。日報・引継ぎノート・LINE履歴・音声記録(許可が必要)など、形式は問いません。時間、場所、影響を具体的に残すことで、上司や第三者の理解を得やすくなります。
ステップ2:DESC法を用いた伝え方
- D(Describe):問題行動の事実を述べる
- E(Express):それによる影響を説明
- S(Specify):具体的にどのように改善してほしいか
- C(Consequence):改善されなかった場合の影響
この方法により、感情を抑えた伝え方が可能になります。
ステップ3:第三者の介入
可能であれば、看護師長や人事、上司を巻き込んだ場でフィードバックを行いましょう。個人間のやり取りにせず、組織的対応へと持ち込むことで公平性と安全性が保たれます。
ステップ4:改善契約・段階的指導
改善計画書を作成し、具体的行動と期限、評価方法を明示しましょう。できれば本人の署名をもらう形で責任の所在を明確化します。その上で、進捗がなければ段階的な注意・配置換え・職務変更など、段階を踏んで対応していきます。
管理者・チームが取るべき中長期的な対策
1. コンピテンシー評価の導入
行動評価を明文化し、年齢に関係なく定量的に業務を評価する基準を整備します。例:報告・連絡・相談の質、チームワーク、エビデンス準拠の実践力など。
2. 組織文化のアップデート
「変化を受け入れることが評価される風土」を創るために、学び直しやリスキリング研修を積極的に実施します。
3. ピアレビュー・360度評価
同僚・後輩・他職種からの多面的な評価制度を導入することで、立場に関係なくフィードバックが機能する環境が整います。
まとめ
理学療法士として働く私たちが、現場で遭遇する“年齢を重ねた問題行動”は非常にセンシティブで、放置してはならない課題です。個人の性格や年齢の問題と片付けるのではなく、「行動」「影響」「対処」という視点から、組織的に取り組むことが重要です。
年齢にかかわらず、変化に対応できる人こそがこれからの医療現場で求められる存在です。そしてその文化を根付かせる第一歩は、今この瞬間の気づきと小さな行動から始まります。
理学療法士として、現場の空気をより良くするために、あなた自身が“変化の種”となることを願っています。
関連サイト
JSPO 日本スポーツ協会
わが国におけるスポーツ統括団体「JSPO(日本スポーツ協会)」の公式サイト。国民体育大会や日本スポーツマスターズの開催、スポーツ少年団の運営など。
公益財団法人日本パラスポーツ協会(JPSA)
日本パラスポーツ協会(JPSA)は、国内における三障がいすべてのスポーツ振興を統括する組織で、障がい者スポーツ大会の開催や奨励、障がい者スポーツ指導者の育成、障がい者のスポーツに関する相談や指導、普及啓発などを行っています。