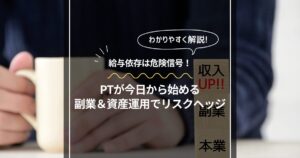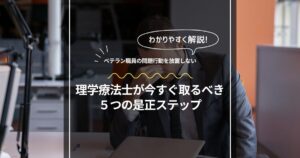- 1. はじめに
- 1.1. 副業による減給処分が現実に起きている
- 1.1.1. 国立病院機構あきた病院のケース(2025年)
- 1.1.2. 小樽市立病院のケース(2024年)
- 1.1.3. 国立病院機構沼田病院の看護師(2022年)
- 1.2. なぜ副業で処分されるのか?法律と就業規則の視点から
- 1.2.1. 労働基準法と副業制限
- 1.2.2. 病院独自の就業規則
- 1.3. 理学療法士が気を付けるべき副業リスク
- 1.3.1. ① 許可を得ずに行う副業
- 1.3.2. ② 本業への支障
- 1.3.3. ③ 競業にあたる副業
- 1.3.4. ④ 病休・育休中の副業
- 1.3.5. ⑤ 品位保持義務違反
- 1.4. 処分されないための対策5選
- 1.4.1. 1. 就業規則を熟読する
- 1.4.2. 2. 事前に上長・人事に相談する
- 1.4.3. 3. 労働時間の管理を徹底する
- 1.4.4. 4. 医療と関係のない副収入源を選ぶ
- 1.4.5. 5. SNS発信は慎重に
- 2. まとめ:副業は正しい知識と手続きで未来を切り拓く手段に
はじめに
理学療法士として日々患者と向き合う中で、「副業で収入を増やしたい」と考える方も多いのではないでしょうか。物価上昇や将来の不安、さらにはキャリアの幅を広げる目的で副業を検討するのは、ごく自然な流れです。しかし、実は副業によって“減給”という処分を受けるケースがあることをご存じでしょうか?本記事では、現役理学療法士を対象に「副業で減給処分を受ける仕組み」と「リスクを回避するための具体策」について、徹底的に解説します。
副業による減給処分が現実に起きている
副業による減給処分は決して都市伝説ではありません。実際に、以下のような事例が報道されています。
国立病院機構あきた病院のケース(2025年)
40代の男性医療従事者がSNSを通じてオンライン講義を実施し、報酬を得ていたことが発覚。病院の就業規則では副業は許可制であったにも関わらず、申請せずに行っていたため、減給処分(0.5日分)を受けました。
小樽市立病院のケース(2024年)
30代の医師が他院で無断アルバイトを行い、さらに病休中も別施設で勤務していたことが判明。停職3カ月という重い処分が下されました。
国立病院機構沼田病院の看護師(2022年)
20代女性が接待を伴う飲食店で働いていたことが発覚。就業規則の品位保持義務違反と判断され、減給処分と同時に退職する形になりました。
このように、たとえ副業の内容がリハビリに関連していても、「無許可」や「勤務時間外での疲労」「病院の信用毀損」などの理由で処分の対象になるリスクがあります。
なぜ副業で処分されるのか?法律と就業規則の視点から
労働基準法と副業制限
労働基準法自体は副業を禁止していません。しかし、企業(病院)は就業規則で副業を制限することが可能です。特に公務員や公的医療機関の職員には、国家公務員法や地方公務員法に基づき、原則として副業が禁止されています。
病院独自の就業規則
理学療法士として勤務する医療法人、社会福祉法人、地方自治体等の医療機関では、次のような規定が多く見られます。
- 副業は原則禁止だが、許可を得た場合に限り可能
- 医療に関する副業は競業避止の観点から不可
- 勤務時間外であっても職場の品位を損なう行為は禁止
このような規定に違反した場合、懲戒処分(戒告、減給、停職、免職など)を受ける可能性があります。
理学療法士が気を付けるべき副業リスク
① 許可を得ずに行う副業
最も典型的なリスクです。「どうせバレないだろう」と安易に始めた副業が、税務調査や内部通報によって発覚し、処分されるケースが後を絶ちません。
② 本業への支障
副業で深夜まで活動し、翌日のリハビリ業務でパフォーマンスが低下するような場合、「本業に支障をきたしている」として減給の対象になることがあります。
③ 競業にあたる副業
例:整形外科クリニックに勤務するPTが、近隣の整体院で働いている場合、患者の流出や病院の営業損失につながると判断される恐れがあります。
④ 病休・育休中の副業
病休や産休中は給与が支給されているため、その期間に副業を行うと「詐取」とみなされることもあります。
⑤ 品位保持義務違反
リハビリ職としての信用を損なう活動(風俗業・過激な動画投稿など)も処分の対象になります。
処分されないための対策5選
1. 就業規則を熟読する
まずは自分が所属する病院の就業規則を確認しましょう。「副業」「兼業」「営利活動」などのキーワードを含む条文がないかをチェックします。
2. 事前に上長・人事に相談する
許可制の場合、口頭だけでなく文書で申請を行いましょう。業務内容、稼働時間、報酬、健康管理への配慮などを明記することがポイントです。
3. 労働時間の管理を徹底する
本業・副業合わせて労働時間が過重になっていないかを見える化しましょう。スマホアプリやApple Watchの活用が有効です。
4. 医療と関係のない副収入源を選ぶ
ブログ運営、教材販売、監修記事の執筆など、直接的な施術を伴わない収入源であれば、競合リスクや患者トラブルも少なく安全です。
5. SNS発信は慎重に
YouTubeやInstagramなどでの発信活動は、個人と職場の線引きを明確に。患者情報や病院名を出さない、医療広告ガイドラインに違反しないことが重要です。
まとめ:副業は正しい知識と手続きで未来を切り拓く手段に
副業=処分ではありません。大切なのは「本業に支障をきたさないこと」と「就業規則を守ること」。正しい手続きを踏めば、理学療法士としての専門性を活かしながら、収入の柱を増やすことは十分に可能です。
副業を始める前に、まずは今の職場のルールを確認し、然るべき手順を踏むこと。その一歩が、あなたの将来を守り、豊かにするための大切なスタートラインとなるのです。
関連サイト
JSPO 日本スポーツ協会
わが国におけるスポーツ統括団体「JSPO(日本スポーツ協会)」の公式サイト。国民体育大会や日本スポーツマスターズの開催、スポーツ少年団の運営など。
公益財団法人日本パラスポーツ協会(JPSA)
日本パラスポーツ協会(JPSA)は、国内における三障がいすべてのスポーツ振興を統括する組織で、障がい者スポーツ大会の開催や奨励、障がい者スポーツ指導者の育成、障がい者のスポーツに関する相談や指導、普及啓発などを行っています。